久しぶりに小説を読んだ。本は時々読むようにしてきていたが、自己啓発本のたぐいばかりになってしまっていて小説を読むのはいつ以来だろうか。記憶に無い。
著者の金原ひとみさんの本を読むのは「蛇にピアス」を発売当初に読んだ以来である。
本書「YABUNONAKA」は、Youtubeで取り上げられていた内容を聞いて読みたくなった。
最近、興味を持って観るものが冤罪を題材にした映画やドキュメンタリー、ニュースとどこか共通しているのではと思った。
「事実」と「真実」の違いとういうか、そもそも定義にもよるとは思うのだけど、「事実」は客観的な視点、「真実」は主観的な視点と捉えるとすると、「事実」は1つだが「真実」は1つとは限らない。
本書はそのことを自分に突きつけてくるような迫力があった。描写がとても効果的だからだろう、登場人物の心理が生々しく伝わってきた。
本の内容に引き込まれるとともに、自身のこれまでを振り返ることにもなってしまい、「事実」を自分に都合良く解釈してきたのではという反省と怖れを感じることとなった。
本の話から逸れてしまうが、50歳の記念にと6月に自分が通っていた大学を見に行った。卒業して以来約30年ぶりの大学近くの駅前は、当時は開かずの踏切だったのに地下鉄化されていた。でも駅前のPARCOは当時から変わらず存在していて、見慣れた風景と始めて見る風景が混在して、何か自分の記憶が曖昧なだけで当時から地下鉄だったんじゃないかなと、現実を受け入れ記憶を否定するような感覚になった。
ここまで来たついでにと大学の4年間を生活の中心に過ごしたアパートを見に行った。アパートまでの道のりも線路沿いに行けばよかったのが、線路自体が無くなっており、これまた記憶にある風景と始めてみる風景が混在していて、懐かしい思いに浸りたいのにそうはさせてくれなかった。
アパートは隣に大家さんの自宅もあったのだが、両方とも取り壊されており、ちょうど建物の新築中だった。あのころのアパートを見て記憶と照らし合わせたかったけど残念。自転車があれば近くの多摩川も行って見たかったが、時間もそれほどの思い入れもなかったので諦めた。あとで気づいたがGooglemapで簡単に住んでいたアパートが既に無くなっていることは確認できた。
本の感想に戻ると、「事実」をどう受け止めるかで「真実」が変わり、「事実」が複数人で共有されるといくつもの異なる「真実」となってしまう。世論は大多数の人が作る「真実」なのかもしれない。でも、世論自体も時代や背景、「事実」の量・質によって変わる。本書では特に時代背景によっても変わりうるということが書かれており、過去に社会的に認められており我慢を強いられていたことも時代が進むにつれ、常識が変わっていくことで、我慢していたことを悔い、自分は間違っていなかったということを主張したいという強い思いが伝わってくる。
冤罪に関しても似たような構造のような気がする。「事実」を組織的な都合の解釈による「真実」として、時には間違った判断になってしまう。最近は組織に所属していることが怖いと感じることもあり、「事実」をどのように捉えることが将来にわたり「真実」として扱われる判断ができるのか、自分の中での判断も反芻してしまい、なかなか自分としての答えも見つからない。
個人の捉え方により、同じ「事実」が違う解釈となるということがあるのは当然ではあるが、それを理解していないと怖いことでもあり、そこで他人との分断や軋轢が生じる可能性がある。そのことを子供たちにも伝えたいが、いかんせん本書は性的描写が多分にあり家族へオススメするのは気が引ける。
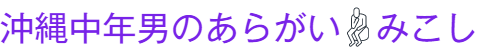
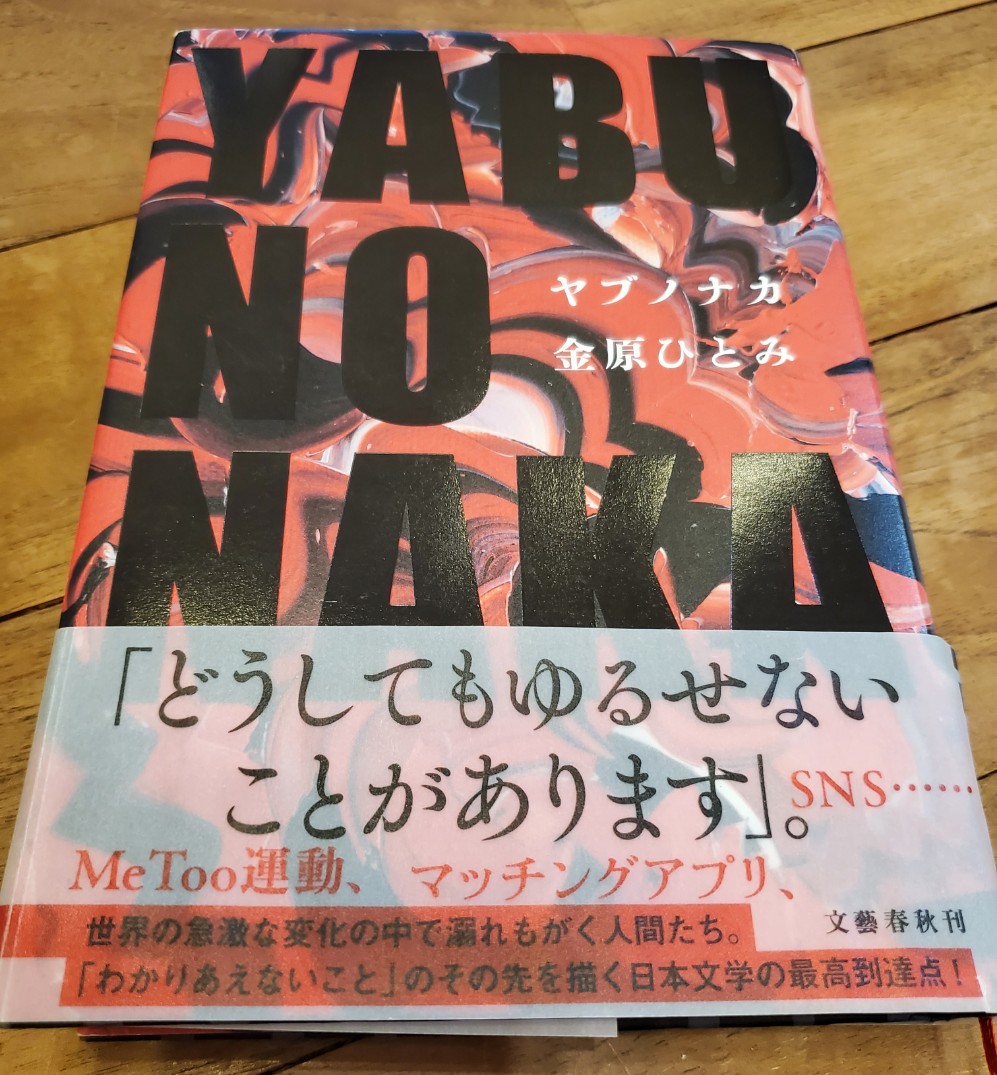
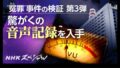

コメント